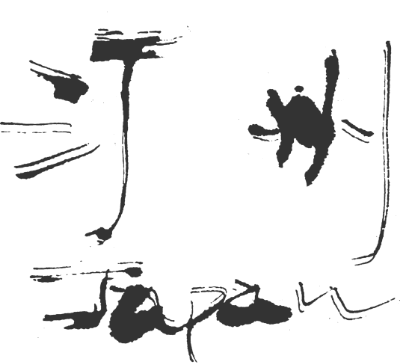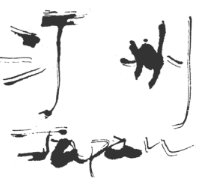レーダーチャート 241023
2024/10/23
正多角形のベース図に複数の測定数値を記す線グラフで、クモの巣グラフとも呼ばれる。たとえば、正五角形上に五教科の点数を表したり、自動車の性能を5項目で表したりする。そのグラフを見ると、この車は快適に加速するし軽量なのが特長で、人や荷物を多くは積載できないのが弱味といえば弱味だというような特徴がよくわかる。
いけばな展を開催するとき、どういう自己評価項目をつくって企画するかが次回の課題だと思うので、仮に5つを設定してみよう。①伝統文化を感じさせる ②いけばなに興味を持ってもらえる ③草月らしさが感じられる ④観客の感性を刺激する ⑤出品者のキャリアや属性が幅広い。
次に、個々の作品が与える印象を考えてみる。①美しい ②明るい ③優しい ④元気だ ⑤強い等々。このとき、出品作品のバリエーションが広ければ、楽しさが溢れる展覧会になると期待されるが、下手をするとまとまりがなく騒々しい展覧会になるリスクもある。
これは、ミュージシャンのアルバムづくりやコンサートについても同様で、テーマの絞り込みとバリエーションの広げ方のバランスが難しい。
飾りじゃないのよ 241022
2024/10/22
いけばな展でのお客様の会話、「ばらまいている、あの汚い土は何?」その人にしてみたら、いけばなは綺麗なものであってほしいという自然な気持ちがあっての発言だろう。「いけばな展にわざわざ来たのに、あんな土くれなんか見せられたら堪らないわ!」という憤りが含まれていたかもしれない。
しかし、芸術の表現は無限だし、作者の方は「綺麗なだけの花だったら、その部屋に綺麗な花柄の壁紙かカーテンでもあればいいの」と、うそぶくに違いない。一般的には汚いよりも綺麗な方がいいという期待があるだろうけれど、ここで指摘しておきたいのは、掃除を済ませた部屋は綺麗だけれど、美しいとは限らないこと。
人間の表情は、起きてから寝るまでに千変万化する。どんな美人だって、腹も立てるしトイレにも行く。くしゃみもすれば涙も涎も流すし、しかめっ面でうつむいているときだってある。それが生きている美しさだ。
同じように、生きているいけばなによっては、悩んでいる花もあれば悔しがっている花もある。要は、いけばな展の会場は、お花畑ではなく、作者の思想や訴えが並んでいる。
目を閉じて 241021
2024/10/21
昨日は、止まない風の中、北条のモンチッチ海岸でいけばなライブを行った。作品は無残にも完成直前に風に押し倒されて、復旧作業を余儀なくされた。昨年も同イベントでいけばなインスタレーションを行ったが、私がつくった「筏いけばな」は風に煽られ、沖まで出ることなく河口に押し戻されて座礁した。願いは叶わないから、より強い願いとして私の心に宿る。
松任谷由実の『瞳を閉じて』という曲は、「風が止んだら沖まで舟を出そう……」で始まる哀しい歌だ。その歌詞では、瞳を閉じて海を眺めるという人を食ったような、けれど私には腑に落ちる不思議な表現がある。日頃から眠たい私だけれど、何かを願うときはことさら、目を閉じて眠るような気配で祈っている。
私は、目を開けていると祈れない。左から右に何か目に映るものがあると、全然集中できないのだ。だから、私が目を閉じているときは集中しているのに、他人から見ると、うとうとと眠りの淵に入りかけているように映るらしい。
目を開けていたら、風も見えない。いけばなライブでは、目を閉じて海風を見なければならなかったのに。
心で願う 241020
2024/10/21
目を見開いていても見えないものがあることを知る人は、少ないかもしれない。どんなに視力が良くても見えないものは見えないし、どんなに視力が悪くても見えている人には見えているものがある。
もう少し深みを覗くと、こっちが見ているとき、あっちから見られている可能性はとても高い。『裏窓』というアルフレッド・ヒッチコック監督の映画を観たとき他人の視線に対する恐怖を実感したが、こっちが見よう見ようとしている場合ほど、あっちからも見よう見ようとされていることを知るべきである。
そういう局面では、全くのところ視力の問題ではなく、「見たい」意識のえげつない強さが勝っているかどうかということで、普通なら見えないものが見えてしまうという欲望の強さの問題なのである。これは裏返すと、「見せたい」という欲求が強ければ強いほど、普通なら見えないものまで見せてしまうということで、見えるか見えないかは、互いに心を開いて見せようとしているか、見たいと思っているかにかかっている。
小手先ではなくそういう気持ちの強さが、当然のこととしていけばなにも表れる。
手を見る 241019
2024/10/19
私は「この枝をこう切ろう」と思って、枝を左手で支え、右手に持ったハサミを凝視しながら枝を切る。よく切れるハサミなので、指を切ってしまったら元も子もない。私の手は私の頭が操る道具である。
すごいなと思うのは、熟練した音楽家たちが手元を見ずに演奏する姿である。彼らの手は、彼らの頭が操っているとはとても思えない。手そのものが“彼として”主体的に演奏しているように見える。卓球選手などもすごい。彼らが球を打つとき、頭が手に対していちいち命令を出していない。待てよ、剣道だってそうではないか!
このように考えたとき、書道や茶道も自分の手元をよく見ていることに思い当たった。手を道具として使っているのは「文科部系」で、手が自身として動いているのは「運動部系」であり、音楽は「運動部系」の仲間なのだ。
これは、自分と時間の関係に由来するのかもしれない。運動も音楽も、試合中や演奏中の流れに対して、自分が勝手に休みを入れることができない。いけばななどは、自分の動作と時間をある程度好き勝手に操ることができる。だから、じっと手を見る暇がある。