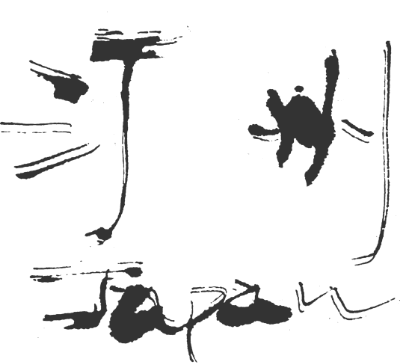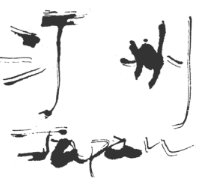花と環境問題 240814
2024/8/14
いけばなをしていると、自然環境保全に関心のある人だろうと思われがちだ。間違ってはいないけれど、信用されても困ってしまう。私は、飲食物に対しても、あまり気にする方ではない。毎日8種類の薬を飲み続けなければならない体は、ほとんど毒されているからだ。地球人も地球も、かなり毒されていると思うのである。
花材がどこで生産されているか、食べる野菜ほどには気にしていない。気にするのならば、「花にも産地表示をしてくれ」とお願いせねばなるまい。実際のところ、花の流通にトレーサビリティは機能していない。
自分が活動する範囲で、多くの人は使う道具や材料について関心があるだろう。購入先や販売先にも関心が高いはずである。しかし、紅麹の問題で明らかになったように、日本国内での製造だから安心だとか、大企業だから安心だというのは幻想だとわかった。また、一般的な知識では、専門的な言質に太刀打ちできないこともわかった。
買う花が、無農薬で栽培されているのか減農薬栽培なのか、ハウス物なのか露地物なのか、どこまで意識的であるべきか、私は姿勢を示せない。
猿真似 240813
2024/8/13
習い事は物真似から始まる。お手本を何度も何度も真似ていく。そのうちに、真似ても面白くない手本や、真似ているうちに共鳴するような気持ちの高ぶる手本が現れて、次第に自分の好みや自分のスタイルも見え始める。
私は、早い時点でいけばなの好みが偏ってきて、自分のスタイルの幅が狭くなってしまった。いけない傾向だった。冒険が苦手だったのか、逆に冒険心が旺盛な自分をわかっていて自己抑制していたのか、安全地帯を飛び出すことをせず、小さな生活を送ってきた。
真似をすることは簡単だというのも、思い違いだった。猿真似は楽ちんだが、しかし、人の作品を真似るというのは、単に作品の見かけを真似るだけではなく制作の背景にある思想や心情を真似なければ、本当に真似たことにはならない。だから、真似たいと思った作品や作者に対する共鳴がなければ、本当の真似事には至らないのである。
ということは、共鳴をもとにした真似には、真似といいながらも本人の心の振動が制作に携わっているから、もう猿真似とはステージが違う。クラシックの楽譜を弾くピアニストも同じだろうか。
自然との闘い 240812
2024/8/12
自然との闘い。パリ五輪で北口榛花選手がやり投げで金メダルを勝ち取った際の、日本のテレビ番組でコメンテーターが取り上げた話題だ。やり投げはもちろん、屋外競技は何でも、気象条件に応じたコンディションづくりが非常に大事である。
小中学校で、私はサッカーをしていた。紳士のスポーツは天候によって試合が中止されることはないという心得を、何度となく聞かされた。それは、人間が自然に対して上位でいることを求めているのか、自然に負けない自己鍛錬が求められているのか、自然を受け容れて与えられた状況を愉しむことを求められているのか、幼い自分にはわからなかった。
さて、いけばな展の会場が屋外の場合、気象状況をとても気にする出展者もいれば、私のように何も気にしない者もいる。気象を気にする人は、どんな会場であっても、アクセスの悪さや集客の困難さ、照明の悪さやエアコンの風など、何かが気になってしょうがない。
いけばなにおける自然とは、闘う対象ではなく花材を提供してもらうパートナーなので、日照りも雨も風もなんのその、楽しくやり過ごすことが肝要だ。
いろいろ試してみること 240811
2024/8/11
パリ五輪で、北口榛花選手がやり投げで金メダルを取った。彼女はジュニア時代に、水泳で全国優勝、バドミントンでも全国優勝を果たしている。その後、やり投げを選んで世界を目指したが思うような成績を挙げられず、水泳のバタフライで名を成した松田選手に教えを乞いに行った。肩の使い方に共通点やヒントがあると睨んだそうだ。
北口選手に止まらず、アスリートは「出稽古」も盛んに取り入れる。コーチを換えることにも躊躇しない。
草月では、生徒都合で先生を換えることが、あまり大っぴらにできない風潮がある。私自身、少年時代に習っていた習字の先生が他界されたとき、紹介された新しい先生に就くことなく、習字そのものをやめた。「道」が付く習い事は、師匠との関係が排他的になってしまうものだろうか。習い事の選択肢が多くなり、人口は減少している状況で、その傾向が変わらないとするならば、それは滅びへの道を行くことになるだろう。
親を換えることは難しい。しかし、昔の「道」の捉え方ではなく、親子関係ではない友人関係に近い新しい「道」をつくる時期にきているようだ。
集い効果 240810
2024/8/11
人が人との関係性を緩やかに保ち、儀礼的ではなく出入り自由な場、いけばな教室の魅力の1つだ。
いけばなは1人でも完結する。作者と鑑賞者を別々に設定する時は2人以上が必要となるが、華道として道を究めようとする時は、作者と鑑賞者は1人2役で十分である。ところが、いけばな教室を主宰しながら感じることは、教える側が1人で教わる側が1人という最少パターンと、教える側が1人で教わる側が複数人というパターンとでは、場の性質が異なってくることだ。
教える側が1人で教わる側が1人の場合、その学びは深くなる。そのときは、互いに相手の人格や性格を意識して対峙することになり、予定調和で意外性は生まれにくい。しかし、一子相伝の極地に到達しそうな可能性は高い。
教える側が1人で教わる側が複数人の場合は、その学びが広くなる。広くなるというのは、教える側も含め参加している1人1人の「気付き」が多くなる。ある1人の何気ない“いけ方”に不意を突かれるとでもいうのだろうか、思い掛けない新鮮な発見をして、おお! その手があったか! と唸ることが多いのだった。