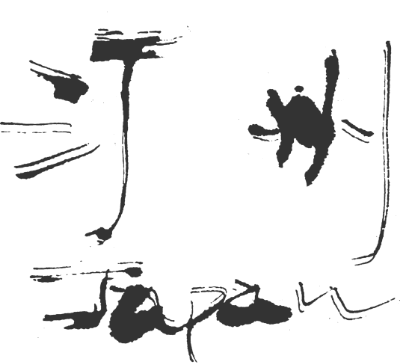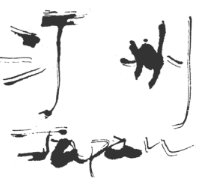枯物をいける 240518
2024/5/18
いけばな展でも、私は枯物花材を多用してきた。消極的な気持ちと、積極的な気持ちの両方があった。消極的な方は、いけばな展の会期中にあまり手入れをしなくて済むこと。積極的な方は、大きい作品をつくるとき、構造を支えるために一定の強さや硬さが必要なことである。
しかし、過去の自分の作品を思い出して、反省することしきりである。枯物は当然のことながら色の彩度が低い。派手やかでなく、静かにくすんだ色味である。絵画でいうモノトーンの画面に近い印象になる。絵画を思い起こせば分かりやすいのは、モノトーンで描くときは、陰影のコントラストを強くせざるを得ない。ところが、いけばなで陰影を出そうと思ってもうまくいかない。枯物花材は明度差も小さいのである。くっきり見せるためには、ボリュームで圧倒するか、着色花材を有効に使わなくてはならない。また、ハイライトもブラックポイントも、スマホの画像処理のようにはつくり出せない。理屈はわかってきた。
そんなわけで、枯物花材を積極的に使うのであれば、色彩以上に光と影(明暗)を意識して操らなければならない。
量が質になる 240517
2024/5/18
私は、いけばなを始めてこのかた、飽き性なので徹底して「型」をマスターしてこなかった。他人に対する興味が薄いから、他人の作品をあまり見なかった。おこがましいことである。だから、私は大したいけばな作品を残せていない。
いろいろ仕事もしてきて、もう退職してしまい、今に至って「量をこなす」大切さがわかるようになった。量をこなすことは情熱にも関係することだと思うので、これまでの私には情熱の量も足りなかったとしか思えない。情熱の量が足りないと、取り組む仕事の量も趣味の量も、人と付き合う友情や愛情の量も足りなくなる。
一握りの天才は、量を問題とせず一気に質の高い成果を出す。とはいえ、天才も凡人も同じだけの人生の時間を持っているのだから、天才は天才的な時間の使い方をしているのかもしれない。凡人はきっと無駄な時間が多いのだ。下手な考え休むに似たりだ。
しかし、いけばなの生徒さんや他の先生を眺めて、ほんとうに他人の作品をよく見ていると舌を巻く。それで、めきめき上手になっていく。やはり、質を上げるためには量が必要なのだとつくづく思う。
技術と情熱 240516
2024/5/18
いけばなの技術が少しは上達してきたと思っている。技術は、学ぶことができるし、積み重ねていくことができる。一度身に付いた技術は、そう簡単に擦り減ることもないはずだ。華道の道は果てしないから、果てしなく技術力は上がっていくだろう。
ところが、何としたことだ! 情熱というやつが、なかなか厄介な代物なのだ。体温が上がったり下がったりするように、自分が自分でコントロールできないところがある。何かのショックですぐに萎えてしまったり、何かの弾みでたちまち燃え盛ったりする。
情熱が乗りに乗っているときは、制作の途中で気付いた失敗に対して、その事実を正面から受け止めて始めからせっせとやり直すことができる。ところが、情熱の火が消えかけていると、だいたいにおいて「ま、いいか」と、良かろうが悪かろうが立ち止まらず振り返らず、いい加減すぐに「できた」と言ってしまう。
技術があると、一定のレベルの物はつくれるだろう。しかし、情熱がないと、それ以上の物はつくれない。情熱があると、時にとんでもない物をつくることができる。仮に技術がないとしても。
「綺麗」の演出 240515
2024/5/18
汚い花より、綺麗な花の方がいいと素直に思う。では、汚いいけばなと綺麗ないけばなは、どっちがいいだろうね? この問いに対しても、少なくとも汚いいけばなは嫌だなあと思う。では、汚い人と綺麗な人のどっちが好き? と聞かれたらどうしよう。「汚いだけの人は嫌いだし、でも、綺麗なだけの人も嫌いだね」そう答えようか。
つまり、綺麗か綺麗でないかというような、イエス・オア・ノーを単純に求めようとする質問のしかた自体がナンセンスであって、そんな問いに答えたところで、別に人生において何の意味もない。
いけばなは、真副控の3つの「主枝」で構造がつくられ、それを取り囲むように「従枝」が何本かいけられる。そして、それが特定の空間に置かれる。もちろん素晴らしく綺麗なバラを一輪挿しに一輪だけいけることもあるだろう。いぜれにせよ、どこにどのように置くかによって景色は大いに変わる。
やはり、いけばなをする人は、総合プロデューサーにならなければならない。「綺麗」のために陰や影をつくり、「綺麗」のために破調も用いて、綺麗なだけの「綺麗」を嫌わなくては!
具象と象徴 240514
2024/5/18
「いければ花は人になる」
これは、初代家元、勅使河原蒼風の言葉だ。「いける」行為が伴うかどうかで、地面から生えていた松が、いけばなという作品に生かされ直して先程までの松ではなくなり、いけた人の人格を纏った存在として立ち現れるのである。
昨日は「松をいけて、松に見えたらダメでしょう」という一節を取り上げて、具体的な花木をいけて抽象化を目指す重要性を考えたが、千利休にまつわる逸話で、庭の朝顔を見に来た豊臣秀吉を迎えるために、庭の朝顔をすべて摘み取って茶室にたった一輪を飾った。この朝顔は、確かに利休の思いと手によって演出されいけられた朝顔なのだが、「朝顔をいけて、朝顔に見えなかったらおかしいでしょう」というくらい朝顔しか見えない。
要は、いける際の意図の問題だ。その一輪の朝顔は、本来一輪だけで庭に咲いているということはないので、その意味で非現実的だ。一輪の花を残して見せるのは、デフォルメ(削除と強調)の極限で、全くもって朝顔にしか見えないいけばなも、この世の具象の朝顔ではなく、別世界の象徴としての朝顔かもしれない。