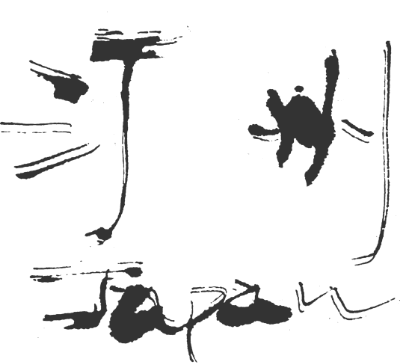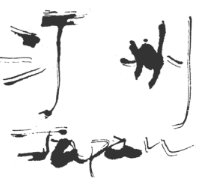理解力 250519
2025/5/19
分かりやすく言おうとすると、尾ひれを端折って簡単な言い回しになる。端的になればいいのに単純なだけの表現になってしまい、結局は真意が伝わらない。
私は、鮮やかでなく大きくない花の方に好みが傾いている。これは、鮮やかで大きい花は好みではないと言っているのとは違う。「玉井くんはなぜ私に冷たいの?」と聞かれて困るのは、私は誰にでも温かくはないというだけのことだからだ。「政治家はなぜみんな嘘をつくの?」と聞かれたら、どんな属性を見ても常に本当のことだけしかしゃべらない人に出会ったことはないしさ、こう返すしかない。
いけばなの良し悪しも単純ではない。論理だてて説明しても納得は得られまい。百聞は一見に如かずとか虎穴に入らずんば虎子を得ずというような、その人が直接的な体験を伴わない限り理解できないものが世の中には多い。
いけばなには厳正なルールブックというものがない。ガイドラインを示すためのテキストはある。修行がランクアップするにつれてテキストの行間を読めるようになってきて、同じ1冊から教えられる質と量も大きくなるというものだ。
極道250518
2025/5/18
茶道、書道、華道、極道。極道の道を極めることを普通の人は避けた方がよさそうだが、相当の覚悟さえあれば一足飛びに行くこともできる。しかし、そこまで極端ではなく、道を極めるという字義通りの意味に取ると、華道で極道に至るためには、人間離れした稽古や修業を積み生活感も日常性もすっかり削ぎ落としたストイックさは求められそうだ。
もしその境地に達することができると、いついかなる局面でも、いけばなの黄金比を易々と表現してしまえるような卓越した技を身に着けているだろう。そうなってしまえば、心に描いたものがそのまま身体に乗り移って表現ができる。これはピアノ演奏でも、弓道でも、茶道でも、体操でも当てはまるのではないだろうか。肩の力を抜いたまま自然体で、彼のあるいは彼女の世界を創出する。
これは商売でも同じで、欲望を抑え純粋にお客様に心を馳せて商品を売る。儲けを度外視しないまでも、儲けには走らない。息をフーッと吐き切って結果を天に委ねる。
いけばなをすることは、こういう、シンプルでぶれない振る舞いができるようになることを求めてもいる。
花を調べる 250517
2025/5/17
図書館は昔、検索エンジンの役割を果たしていた。本を貸し出すだけでなく、レファレンス・サービスがあった。特に国会図書館は充実と呼ぶ以上の充実度で、あるとき国会議員の支持者から「息子の卒論を助けてくれ」という依頼が入り、下っ端秘書をしていた私にお鉢が回ってきた。
議員にとって国会図書館は知識の泉で、些細なことを聞くのは逆にはばかられたが、困れば何でも調べてくれた。国会での質問や答弁のために重宝するわけだ。質問をどのように投げるかによって、回答の内容と量も変わってくるので、質問のしかた次第で、大学生の書く卒論ごときは数日間で仕上がってしまうのであった。さすが国立国会図書館である。
質問のしかたが大事なことは、現在の生成AIを使う際も当てはまるだろう。質問が漠然としていると、調べ方も漠然とする。何かを調べるときに、仮説を立てておいてからその真偽や成否の検討を始めると、当たりを引きやすい。
ありがたいことに、草月には『現代いけばな花材事典』があって、植物に対する自分の下手な検索よりも、知りたいことが丸ごとわかる優れモノだ。
はないけ 250516
2025/5/17
カレーライスという言い方とライスカレーという言い方のどちらが正しいか、中学生くらいのときだろうか、友だちと議論になった。そのときマセた友だちが、前(頭)にくる語が後ろの語を修飾するから、カレーライスはカレーをかけた御飯の意で、ライスカレーは御飯を添えたカレーだぞ、みたいなことでみんなを唸らせたように思う。
初めて上京して暮らすようになったとき、徒歩圏内に「二幸」という食堂を見つけた。トンカツから酢豚、塩サバからハンバーグまで定食メニューを幅広く展開していて、学生アパートの隣人たちとお世話になった。私はレバニラ定食を頻繁に注文した。仲間の1人が、オレは田舎に住んでた頃からニラレバと呼んだけどなあと言う。私は少年時代に知ったうんちくをかざし、この店のメニューは少量のレバーを混ぜ込んで炒めたニラである、従ってレバニラなのであると結論付けてやった。
一度気になってしまうと放っておけない性格だから、いけばなはいけられた花である? 一方、はないけは花をいけることである? 全くの言葉遊びだと割り切ってあなたはどっちを選びますか?
木を見て森を見ず 250515
2025/5/15
花が「いけばな」になるというのは、花という植物存在から、作品という意思のかたまりになるということ。初めに花としてただそこにいて、人の気持ちなど何も込められていない状態から、いけばなになった途端に花そのものの存在が消えて、「私」の意思で形づくられた「私」の分身がそこに出現するのだ。
いけばなを見る側の人に強く求めることはしないとしても、いけばなは花を1本、2本、3本……と足し算したものではなくて、掛け算によって花ではない新しい何かが表されていると知っていただけると幸いだ。花を足し算で見る見方は「木を見て森を見ず」という見方で、木を何十本も足したところで森の全貌は見えてこない。
ただ、いけばなの場合は引き算をしていることもあるから、裏事情は単純ではない。
制作過程で一旦は森をつくっておきながら、どんどん伐採していって開墾された大地に一本松が残った、みたいないけばなもある。初めから立っていた松と同じ松に見えたとしても、周りの松が消失することによって、それは例えば祈念の対象の松として新しく意味づけされて変身しているのだ。