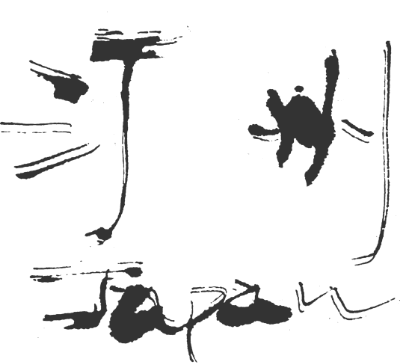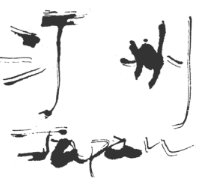秘密の花 250807
2025/8/8
草月の勅使河原蒼風を知って、いけばなには奥義があるのだということを強く思う。その奥義は、特に秘密めいたものではないのに、ただそれを言葉にして説明しがたいというだけで敬遠されがちだ。そして、奥義を理解している(または無自覚に体得している)かどうかは、生活の便宜上いけばなをしている者にとっては、ほとんど意味のない雑音でしかない。
身も蓋もない言い方をすると、何ものをも突き詰めるというやり方は、健やかな生活の場においては無意味で面倒臭い処世術なのである。
さて、「秘すれば花なり」の意味を、今ではAIが見事に回答してくれる。その回答自体に秘したものがないから、それを鵜呑みにすると、秘すという行為が単に隠すことと同義の狭い意味合いになってしまう。隠すことで見る人の興味を深めるというのでは、ストリップ劇場の説明と同じことになる。ちなみに、私はストリップにもプロレスにも、その演出と演技に一目置いているが。
世阿弥が能楽を論じた『風姿花伝』のタイトルの「花」は、「秘すれば花」の「花」同様、その一語に無限の意を持たせていると思う。
いけばなを知る 250806
2025/8/7
いけばなを習い始めて25年、だいたい3周くらい陸上トラックを回ったような感じ。同じトラックを周回していて、それでも1周毎に知識の深さも見える景色も変わるものである。1周目は知識がないから、脇目をふる余裕すらなかった。2周目は知識が足りないから、ムダな考えやムラのある行動が多かった。3周目で解ったような気になって、一生懸命さが足りなかった。
そしていま、4周目に入ったところだ。ここに来て、いけばなをするためにどうしても知らなくてはならないということはあまりないことを知る。それよりも、自分で考えて自分が決めるという態度で臨むことが、いかに難しいことかを知った。我こそはと気負うわけでなく、逆に師匠の言うことが絶対でもない。まして、家元でさえ、自分のスタイルと瓜二つのいけばなを誰かにやられたら、変な気分になることはあっても嬉しくないだろう。
知らないことには一切影響を受けなくて済むというのに、知れば知るほど、知ったことにがんじがらめになる。
真面目な人は、他人の作品を調べるし参考にする。それでいいのだろうが、よくもない。
好きな理由 250805
2025/8/5
世の中わからないことだらけ。真偽・善悪・美醜についてさえ、やすやすとは説明できないというのに、好き嫌いの理由を説明することなどまっとうにできるはずもない。
陽が傾いた夕景が好きだというのはわかってもらえたとしても、夜明け前の黎明より好きなわけは? と聞かれたら、「イヤなんとなく、自分は夜型人間だから朝の景色はあまり見たことがないんよ」くらいの、いい加減な答えしかできない。しかし、よく考えてみると昔は初日の出を見に出掛けていたくらいだから、朝陽の反射が少しずつ広がっていく川面の景色など、それはもう大好きなのだ。
なぜ、それが好きですか? と聞かれて、いけばなが好きな理由をちゃんと答えられた試しもない。決定的な答えがないから、いろいろな角度から説明しようとして、原稿用紙2枚分くらいのボリュームになってしまう。話す方も聞く方もたまったものではない。
なぜアイスクリームが好きなのか。なぜパンクロックの音は好きなのに、クマゼミやアブラゼミの声は好きじゃないのか。甲子園(高校野球)が始まると中継を見てしまうのはなぜ? なぜだろう。
努力の天才 250804
2025/8/5
Kさんは努力の天才である。2年前のある日、いけばな教室に来始めた。以降、忘れた頃になるとやって来る。私も積極的に誘ったりしない。ところが、いけばな展や作品の公開機会があると、必ず「やってもいいんですか、わたし」と、前のめりで迫ってくる。
そんなKさんは、先日ハワイアンのチームにも加わり、11月の公演で早くも初舞台を踏むらしい。他人が聞いたら「気が多い娘さんだこと!」と、否定的に言われかねない。しかし、駅伝を走ったりバトン部だったりというキャリアを知っていると、別に不思議な気はしない。おそらく彼女はずっと全力で試しているのだ、あらゆる人生の可能性を。
Kさんは稽古に来た時、こちらが心配になるほど時間感覚をなくして集中する。努力の天才は、額に汗かいて頑張るということをしない。雑音を遮断して見たいものと聞きたいことだけに神経を集中するから、呑み込みが特別早い。稽古ノートの書き込みの緻密さにも、腕の上達は裏打ちされる。
そうして今日、彼女の仕上がった作品を時計の針で5分だけ左に回すのを見て言うのだ。「先生、さすがです!」
留保と拒絶 250803
2025/8/4
いけばな教室の場で、おじさんおばさんに交じえて高校1年生と話していて、考えさせられることがあった。
昭和世代にとって3世代同居は珍しくなく、表面的には理解できない素振りをみせていたことも否定はできないが、祖父と孫の間でも分かり合える共通感覚や考え方があった。高校1年の彼は“おばあちゃん子”なので、自分はずっと上の世代も理解できると言う。しかし「もう今の小学生の感覚はわからない」らしく、同世代と呼べるのは上下2~3年くらいの同年代でしかない。
私の子どもの頃は、親や先生など年長者の権威が強く、ある部分では同調を装うことが世渡りには必要だった。また、世界の情報化が進んでおらず未知なる存在も多かったから、異質なものや不明なものに出会うと一旦留保するというのが、コミュニケーションのスタイルだった。それに対して現代社会と現代人のコミュニケーションは、異物に対して拒絶を示す。
さて、高校1年の彼は特別である。草月テキストの記述や私のアドバイスを一度は必ず留保し、「ちょっと遊んでみていいですか?」と別の角度から攻めてくるのだ。